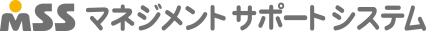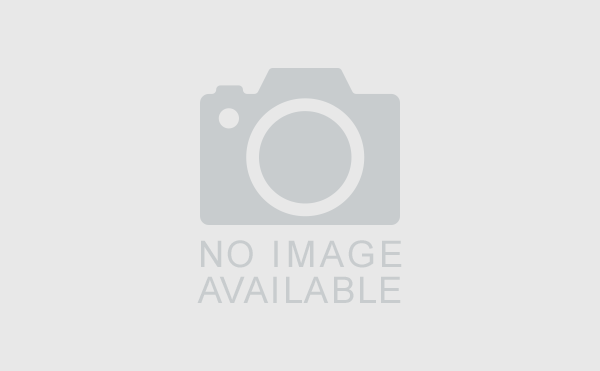【VOZ.158】60歳の壁論 ~正社員との格差~
4月に入り新年度を迎える企業や組織が多い時期になりました。新年度にあたり新入社員を受け入れる時期でもあり、この時期は新入社員にスポットが当たりがちですが、一方では定年退職者を送り出す時期でもあります。
定年退職では、高年齢者雇用安定法の経過措置が終わり、この4月からは希望者全員の65歳までの雇用が完全義務化されました。この企業義務の雇用確保には、1.定年制の廃止、2.65歳まで定年引上げ、3.継続雇用制度の導入が3手法とされます。このうち、厚生労働省「高年齢者雇用状況等報告」によると、それぞれの採用率は、定年制の廃止は3.9%と低く、次いで65歳まで定年引上げは28.7%、継続雇用の制度導入が67.4%と最も高くなっています。
約7割弱の採用率であった継続雇用の制度導入には、いわゆる「60歳の壁」があるといわれています。それは、あらゆる業界業種で人手不足が大きな課題でもあり、労働力が減る中でベテラン社員の活用は必須ともいえますが、60歳以降の処遇面に存在する「壁」です。
厚生労働省などの官庁統計では、大企業を中心に60歳を境に「賃金が3割前後減っている」とされています。公務員でも「60歳以後の俸給7割」が既に規定されており、「3割減」が官民共通の基準になりつつあるようです。「労働政策研究・研修機構の調査結果」によると、60歳以降の仕事内容について「以前と全く同じ」が44%、「内容は同じで責任が軽い」が38%で合わせて8割以上が「仕事内容に変化がない」と答えています。にもかかわらず給料が減額されるのが現状です。私の身近な知人の例では、大手上場企業のメーカー勤務者で55歳で役職定年、60歳以降の継続雇用では3割減ではなく7割減という例もありました。
賃金減については、労使間で裁判でも争われるケースが多くあり、条件によりますが最高裁では賃金減を許容した司法判断が背景にあるともされています。「仕事は同じで正社員と格差あり」という点では、同一労働同一賃金の根拠法である「パート・有期雇用労働法」では、正社員と再雇用者の賃金格差について、職務内容、配置変更の範囲、その他の事情の3点を勘案して合理性を判断するとされているので、一概には比較はできないとされています。
また、60歳以降に減額された側の心境の変化として、「60代の就業実態調査」(パーソナル総合研究所2024年)では、給料ダウンによる変化として最も多かったのは「モチベーションが下がった」(56.7%)、次いで「自分の価値が下がったと感じる」(49.0%)、「会社に対する忠誠心が下がった」(46.2%)と続いています。」
企業や組織の状況にもよりますが、この「60歳の壁」以外にも雇用する側とされる側の労使間においては、クリアしなければならない諸々の課題があります。
<2025年4月shiba>
※今年度の新入社員研修は2社担当します